「何が言いたいの?」とならない!初心者におすすめの文章構成【SDS法】
ブログ記事を書いていると、「説明が長くなりすぎて、結局何を伝えたかったのか分からなくなった…」と悩んだ経験はありませんか?
そんなときに役立つのが SDS法 という文章のフレームワークです。シンプルで使いやすいので、特に初心者ブロガーにおすすめです。
SDS法とは?
SDS法とは、文章を
概要(Summary) → 詳細(Details) → まとめ(Summary)
の順で組み立てる方法です。
最初に全体像を示し、次に詳しく説明し、最後に再度要点をまとめる。とてもシンプルですが、読み手にとってわかりやすく、情報が頭に残りやすい構成です。
ニュース記事、スピーチ、学会発表などでもよく使われている“定番の型”です。
SDS法の流れを実例で解説
1. 概要(Summary)
最初に「この記事で伝えたいこと」を短く提示します。
冒頭を読んだだけでゴールが見えると、読者は安心して本文を読み進めてくれます。
例
「SDS法を使えば、短い文章でも要点を整理してわかりやすく伝えられます。」
2. 詳細(Details)
次に、その概要を補強する情報を出します。
根拠や具体例を示すことで、読者の理解度と納得感がアップします。
例
「SDS法は『冒頭で全体像を示す → 中盤で詳細を補足 → 最後に要点を再確認』という流れです。
たとえば『副業ブログは稼げるのか?』というテーマなら、冒頭で“稼げる”と結論を出し、本文で収益データや体験談を補強し、最後に『だから副業ブログは収益化可能』とまとめると、スッキリ読めます。」
3. まとめ(Summary)
最後に再び要点を短くまとめます。繰り返すことで記憶に残りやすく、読後感もスッキリします。
例
「以上のように、SDS法を意識するだけで、記事の焦点がブレずに、要点を短時間で伝えられるようになります。」
SDS法を使うメリット
-
短時間で伝わる文章が書ける
-
読者が全体像をつかみやすい
-
記事がダラダラせず、一貫性が出る
-
プレゼンや説明文、短い記事との相性が良い
特に「初心者ブロガー」がありがちな“結論が見えない長文”を防げるのが大きなポイントです。
PREP法との違いと使い分け
前回紹介した PREP法 は、
-
結論(Point) → 理由(Reason) → 具体例(Example) → 結論(Point)
という流れで、深掘り解説に向いています。
一方 SDS法 は、
-
概要(Summary) → 詳細(Details) → まとめ(Summary)
という流れで、短く要点を整理したいときに最適です。
👉 使い分けの目安:
-
PREP法:じっくり論理的に説得したい記事(商品レビュー、ノウハウ記事など)
-
SDS法:サクッと要点を伝えたい記事(ニュース要約、時事ネタ、短い体験談など)
すぐ使える!SDS法テンプレート
-
概要(Summary):この記事で伝えたいことは○○です。
-
詳細(Details):その理由は○○で、具体的には△△という事例があります。
-
まとめ(Summary):以上のように、○○だからこそ□□なのです。
この型をそのままコピペして埋めれば、初心者でも整理された文章になります。
まとめ
SDS法は「概要 → 詳細 → まとめ」というシンプルな流れで、初心者でもスッキリした記事が書ける便利なフレームワークです。
長文で結論がぼやけがちな人や、短く分かりやすく伝えたい記事を書きたい人には特におすすめ。
文章に自信がない方こそ、まずはSDS法を“型”として取り入れてみましょう。
別の方法として、以下の記事をご覧ください。
読みやすい記事構成のコツ【PREP法で解説】
読みやすい記事構成のコツ【ストーリーテリング法で解説】
また、それぞれの方法(PREP法、SDS法、ストーリーテリング法)をまとめた記事もあります!!
読みやすい記事構成のコツ【3つの文章構成法を比較】

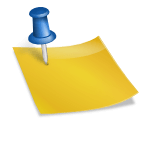
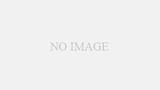
コメント